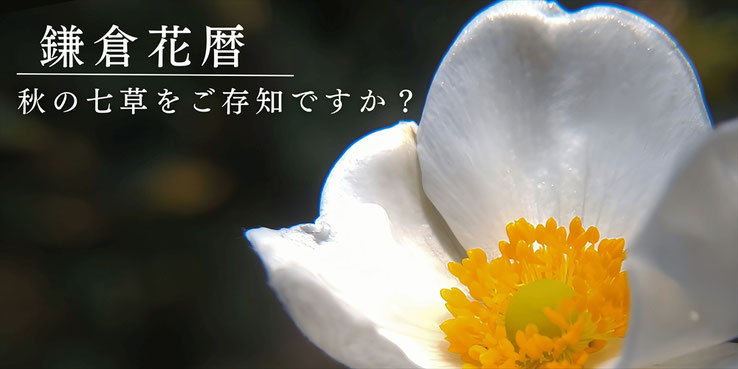
Written by Mieko☆
春の七草と秋の七草、違いはご存知でしょうか?
今回は鎌倉の寺院で観られる花々についてもご紹介していきたいと思います。
●春の七草
1月7日に食される「七草粥(ななくさがゆ)」に入れる7種類の若菜のことをいう。つまり食用となる植物です。七草粥は現在でも“無病息災”を願って食べられているだけあり、それぞれに薬効があります。
●秋の七草
秋を代表する7種類の草花のことであり、食されるものではない。基本的には観賞用の植物(「葛(くず)」「女郎花(おみなえし)」は薬用にされることもある)である。
これらは奈良時代の『万葉集』に収められている、山上憶良(やまのうえのおくら)の歌「萩が花 尾花 葛花 撫子の花 女郎花 また藤袴 朝顔の花」に由来。
ただし、朝顔(あさがお)は私たちに馴染みの朝顔とは違っていて、桔梗(ききょう)という説がつよいそうです。
季節の訪れを感じ、目や香りから日本人を癒してきた秋の七草。
皆様も奈良時代の人達と同じ様に感じては如何でしょうか?
私が毎年秋を愛でる為に訪れる場所2か所をご案内しましょう。
●浄智寺
小道へ入り少し進むと、浄智寺の「山門」が見えてきますが、ここからの景色は絶景です!
最初に見る小さな池も水が澄んでいて、鎌倉石の石段と大きな木々に囲まれた参道に癒されます。
ススキやシュウメイギクが風になびきます。
大きなイチョウの木の根元には沢山の銀杏が…
●英勝寺
門前にススキがあしらわれており、ヒガンバナの時期には鐘楼を取り囲む様に、一面真っ赤に彩られて行きます。
英勝寺の鐘楼は、めずらしい袴腰(はかまごし)鐘楼というもので、鐘の全部が見えないようになっていますが、かえって鐘の音が袴腰の内部で反響して、大きく聞こえるそうです。
行かれる際は、チェックしてみてください。














コメントをお書きください